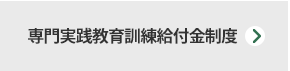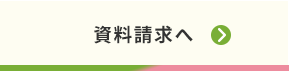学校からのメッセージ・沿革
学校からのメッセージ

学校長 川端 浩

副学校長 上南 雪野
看護師・助産師をめざす皆さんへ
看護師・助産師は、人の生命の尊さに向き合い、喜びや苦悩といった様々な感情に寄り添います。そしてどのような時であっても安心して暮らせるよう、その人らしい生活、心や身体を統合して考え、専門的な支援をしています。
当校では、看護実践に必要な知識・技術・態度を学びます。看護実践では、相手の反応(サイン)に気づき(感じ)、その意味を考え、行動することを大切にしています。
看護師をめざす高校生・他学部で学んだ大学生・社会人経験者の皆さん!助産師をめざす皆さん!
先輩や同級生、助産学科と看護学科双方の学生と学びあい、教員や講師、実習指導担当者と関わり合いながら一緒に考え、内省し成長していきましょう。信頼される看護職者として成長したいと志している人たちをお待ちしております。
学校の沿革
沿革
本校は、厚生省(現厚生労働省)所管のもと昭和24年4月に国立京都病院に附属高等看護学院として1学年定員30名で開設。学校創設にあたっては、アメリカのビリーハーター女史の直接指導をうけて開校。
昭和44年4月に助産婦科(定員35名)新設に伴い国立京都病院附属看護助産学院と名称変更。
平成16年4月には、国立療養所宇多野病院附属看護学校と国立療養所南京都病院附属看護学校と統合、看護学科1学年定員80名の大型校となり、校舎も助産学科との教育ゾーンへと新築・移転。また設置主体が厚生労働省から独立行政法人国立病院機構に移管され、名称は独立行政法人国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校に変更。
創設以来の伝統を引き継ぎ、なお新しいカリキュラムを開拓しつつ看護専門職業人として社会に貢献できる有能な人材育成を目指している。
| 昭和24年4月1日 | 国立京都病院附属高等看護学院として開設 1学年定員30名 総定員90名 |
|---|---|
| 昭和43年4月1日 | 1学年定員50名 総定員150名 |
| 昭和44年4月1日 | 助産婦科の附設 1学年定員35名 総定員35名 国立京都病院附属高等看護助産学院に名称変更 |
| 昭和50年4月1日 | 国立京都病院附属看護助産学校に名称変更 |
| 昭和51年4月1日 | 専修学校(専門課程)に認定 |
| 平成16年4月1日 | 国立療養所宇多野病院附属看護学校(3年課程)と 国立療養所南京都病院附属看護学校(2年課程)と3校が統合、 大型校となり独立行政法人国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校に 名称変更 看護学科 1学年定員80名 総定員240名 助産学科 1学年定員35名 総定員 35名 |
| 平成27年4月1日 | 助産学科定員 25名 総定員 25名 |
| 令和3年4月1日 | 助産学科定員 18名 総定員 18名 |
卒業生数(令和7年3月31日現在)
- 看護学科(1回生~53回生)
- 1,968名
- 看護学科(1回生~21回生)
- 1,611名(統合後)
- 助産学科(1回生~56回生)
- 1,551名
当校の紹介
国立病院機構は全国に140の病院を持つ日本最大の医療ネットワークです。京都医療センターは高度急性期総合医療施設として幅広い機能と役割を担う施設であり、病院と学校は密接に連携をとり教育活動を行なっています。
国民にとって健康で文化的な生活ができることは、国の基盤であり病気や外傷の時には安心して充分な医療を受けられることが願いです。看護職は人の命に向き合い、専門的な知識と技術で患者さんを支援する存在です。
本校では、看護師、助産師としての知識・技術を修得することはもとより、我が国の医療問題を考え、仲間と共にその改善を目指すような医療人に育ってほしいと期待し、育成に努めています。